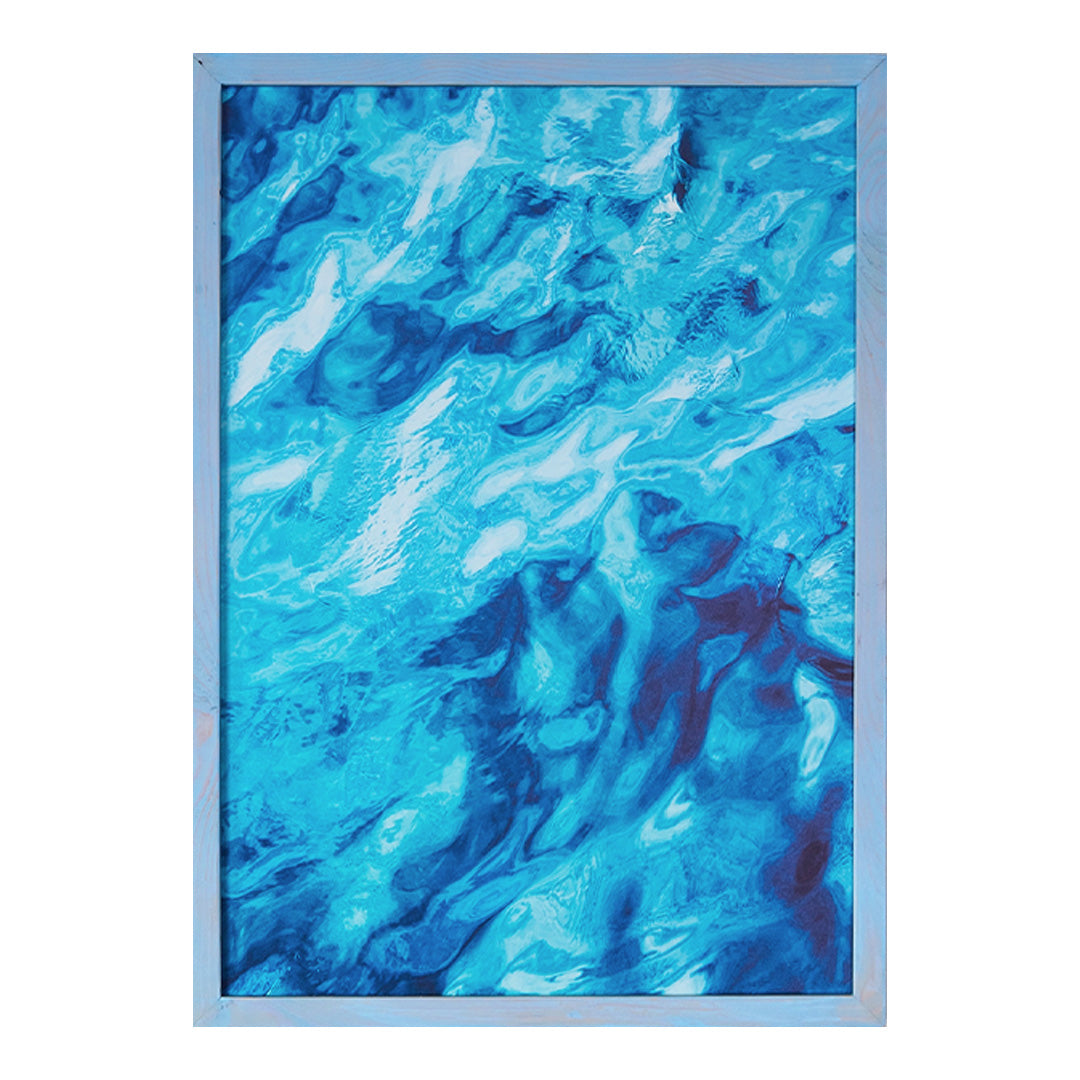写実主義とは?|社会を描く、生きた芸術
投稿日:(月)

目次
こんにちは。WASABI運営事務局のシナモリです。
美術の様式とその評価は、戦争や革命など社会情勢に伴って変容してきました。
どの時代の作品にも、芸術家たちの想いや試みを感じることができます。
特に写実主義は、社会の現実を描きだそうとする強い意志を持っていました。
今回は、写実主義の概要と作品について解説していきます。
概要:写実主義とは
写実主義は19世紀のフランスを中心に広まった思想で、現実をありのままに描こうとする芸術様式です。
画家ギュスターヴ・クールベは、「己の目で見たものを己の感性で描き、生きた芸術を創りたい」という理念を掲げました。
美術だけでなく文学にも取り入れられ、ドストエフスキー、バルザック、スタンダール、ディケンズなどの作家が代表的です。

出典:Britannica
新古典主義と相対する表現方法でしたが、その評価が変わり始めたきっかけは、ヨーロッパ全土に影響を与えた産業革命です。
機械化で産業は急速に進歩し、農業革命により仕事を失った労働者が都市部に溢れます。
資本家階級と労働者階級の間には、大きな経済格差が生まれました。
そのため人々は、ドラマチックで美化された作品に批判的感情を抱くようになります。
こうして、ロマン主義の反動から社会の状況を客観的に見つめ、表現する芸術が広がっていきました。
代表的な画家たち
写実主義は、印象派だけでなく近現代のアーティストにも様々な影響を与えています。そして彼ら自身も、ルネサンスの巨匠や異国の芸術から学びを得ました。
今回は3人の画家を中心に、写実主義の作品と変遷を見ていきましょう。
ジャン=フランソワ・ミレー

ジャン=フランソワ・ミレー
18歳から画塾に通い、パリの国立美術学校に進学します。
師の影響で歴史画家を志しますが、授業にはあまり出席せず、美術館で模写に明け暮れる日々でした。やがて奨学金を打ち切られて退学し、パリを去ります。
翌年、サロンに出品した絵が入選し、肖像画家として活動し始めます。
2度の結婚に伴いパリとシェルブールを移動しながら、生活のために裸婦像を売るようになったミレー。しかし本来描きたいテーマではなく、葛藤の末に画題の転向を決意しました。
この頃、後のバルビゾン派の仲間や支援者と出会い、交流するようになります。
農民を描く画家

ジャン=フランソワ・ミレー 『箕をふるう人』 / ナショナル・ギャラリー
この絵を発表した当時は、2月革命により王政から共和制へと社会が大きく動いていました。
革命の主体となったのは労働者階級であり、描かれている農民の衣服がトリコロールの配色だったことも、高評価のポイントでした。
これにより共和国政府からの注文なども入り、活路を見出していきました。

ジャン=フランソワ・ミレー 『種まく人』 / ボストン美術館
都市を離れて自然風景や農民の姿を描いた画家たちは、バルビゾン派と呼ばれるようになりました。
この地で代表作の一つ『種まく人』を描きますが、今度は農民という画題が社会批判的メッセージを含んでいるとして、物議を醸します。
革命後で情勢が揺れており、労働者とブルジョワジーの意見は対立していました。
そのような中でも評価に流されることなく、ミレーは自分の描くものを選んでいきました。
ゴッホは伝記を読んでミレーに強い憧れを抱き、オマージュ作品を描いています。

ゴッホの隠れた傑作「種をまく人」作品から見えるミレーの影響とは?

ジャン=フランソワ・ミレー 『落穂拾い』 / オルセー美術館
収穫後の畑に残った穂を拾う、貧しい農婦たちの姿を描いた作品です。
19世紀フランスの農村には、旧約聖書レビ記に由来する慣習があり、落穂拾いという光景が見られていました。
“あなたがたの地の穀物を刈り入れるときは、その刈入れにあたって、畑のすみずみまで刈りつくしてはならない。
またあなたの穀物の落ち穂を拾ってはならない。
貧しい者と寄留者のために、それを残しておかなければならない。”
引用: 旧約聖書『レビ記』23-22
この作品にも、政治への批判だとする意見と、農民画の美徳を讃える声とがありました。

ジャン=フランソワ・ミレー 『晩鐘』 / オルセー美術館
自身も農家に生まれたミレーは、祖母との思い出をこの作品に込めています。
賛否両論を受けつつも、懸命に生きる農民や労働者の姿を見つめ続けました。

ミレーの代表作「晩鐘」とは?その魅力から壮絶なオークションまで解説
シュルレアリスムの画家ダリは、この『晩鐘』という作品に言い知れぬ恐怖を抱いたそうです。
祈る様子や地面に置かれた籠から死を連想し、このモチーフを複数の作品に描いています。

サルバドール・ダリ 『建築学的ミレーの「晩鐘」』 / ソフィア王妃芸術センター

サルバドール・ダリ 『たそがれの隔世遺伝』 / ベルン美術館
しかし、秀逸な画力と視点で描かれた彼の作品は、時代を超えて多くの芸術家からリスペクトされました。
ギュスターヴ・クールベ

ギュスターヴ・クールベ
中学生でデッサンの基礎を学び、高校に通いながら画家に師事しました。
大学の法学部に入りますが、親の期待とは裏腹に画家の道に進むことを決め、画塾に通います。
この画塾では、コローやマネの他、後に印象派と呼ばれる画家たちも学んでいました。

ギュスターヴ・クールベ 『オルナンの食休み』 / リール美術館
そして5年後に描いた『オルナンの食休み』が評価を受け、国の買い上げ作品となりました。
ところが、1851年に出品した『オルナンの埋葬』は、批評家たちから「醜い」「見苦しい」と酷評されてしまいます。
ナポレオン3世の即位により、社会が保守派に傾いていたことも影響していました。

ギュスターヴ・クールベ 『オルナンの埋葬』 / オルセー美術館
神や聖人、英雄などを描く伝統的な「歴史画」という定義を、一般市民の絵に用いたため激しく非難されます。
しかし、民衆はクールベの革新的な作風を支持しました。
実際の出席者と葬儀の様子をありのままに描き、人物の感情を大袈裟に表してはいません。
現在を生きる人々の営みも時が経てば歴史画になると考え、クールベは堂々と描いたのです。
彼はこの作品を「ロマン主義の埋葬でもある」と述べ、新たな写実派の芸術を先導していくことになります。
世界初の個展開催

クールベの個展会場
そこでクールベは、なんと万博会場の近くにパビリオンを建て、入場料を設定して自分の作品を展示しました。
それまで画家単独の展覧会は行われたことがなく、これが世界初の個展とされています。
また、この個展の目録に書かれたクールベの文章は、「レアリスム宣言」として写実主義の理念を集約したものになっています。

ギュスターヴ・クールベ 『画家のアトリエ』 / オルセー美術館
『画家のアトリエ』は、クールベ自身が「寓意画」と定義しています。
正式な題名は『画家のアトリエ:我が芸術的(また倫理的)生活の七年に及ぶ一時期を定義する写実的寓意画』です。
キャンバスに向かうクールベ自身を中心に、右側には支援者や友人、左側には現実社会を生きる人々の姿を配しています。
アカデミズムの象徴とされるヌードモデルに背を向け、「私はこれからも味方の応援を支えに、社会の現実を描いていく」という決意が感じられます。
徹底した現実主義
クールベは「天使など見たことがないから描かない」と言う程の現実主義者でしたが、社会問題だけでなく、人間の性的な側面も淡々と表現しました。
1866年には、19世紀で最もスキャンダラスな作品とされる『世界の起源』を描き、大きな衝撃を与えました。
横たわる女性の下半身をあらわに描いたもので、全ての人間が生まれた場所=起源だという究極の写実表現だと言えます。
なお、日本では『世界の起源』をオマージュしたインスタレーションが展示されています。
クールベが表した写実主義が、新たな解釈で現代アートに示されていることは、非常に感慨深いものがあります。

アニッシュ・カプーア 『L'Origine du monde』 / 金沢21世紀美術館
自然風景などの描写も卓越しており、確かな画力と体制に媚びない姿勢には、遠巻きながら印象派の画家たちも憧れの目を向けていました。
エドゥアール・マネ

エドゥアール・マネ
クールベ同様、法律家になることを嘱望されていましたが、芸術の道を選び修行に励みます。
1861年にサロンで初入選した『スペインの歌手』は高評価を得ますが、その後の作品では数多くのスキャンダルを巻き起こしました。

エドゥアール・マネ 『草上の昼食』 / オルセー美術館
この作品は絵画の伝統に反しているとして、大批判を受けることになります。
それは、全裸で描かれている女性が現実の人間であったためです。
当時、裸体を描いてもよいとされるのは、神話や聖書の登場人物に限られていました。

マルカントニオ・ライモンディ 『パリスの審判』 / フランス王立図書館
画面右下の3人が、『草上の昼食』に引用されていることがわかります。
また、幼少期からルーヴル美術館を訪れていたマネは、ティツィアーノの『田園の奏楽』からも着想を得ました。

ティツィアーノ 『田園の奏楽』 / ルーヴル美術館
過去の芸術と現代人の姿を重ね合わせたオマージュ表現でしたが、アカデミズムを重んじる人々からは怒りを買いました。
社会の現実を描く

エドゥアール・マネ 『オランピア』 / オルセー美術館
題名の『オランピア』は、源氏名として代表的な名前でした。
首のチョーカーや腕輪など、娼婦の間で流行した装飾品を身に付けています。
社会の陰を題材にしたことに加え、日本の浮世絵を取り入れた平板な描き方も非難の対象となりました。
顔は女性画家ヴィクトリーヌ・ムーランのものであり、彼女は『草上の昼食』ほか、複数のマネ作品でモデルになっています。

ヴィクトリーヌ・ムーラン

ティツィアーノ 『ウルビーノのヴィーナス』 / ウフィッツィ美術館
全体の構図と女中の存在、足元に動物がいる点は共通しています。
ただし、忠誠心を象徴する犬に対し、マネが描いた猫は不道徳、奔放さを表します。

エドゥアール・マネ 『オランピア』 / オルセー美術館
意図して伝統的手法に背いたわけではないのですが、批判の声は止むことがありませんでした。
失意の中スペインへ向かったマネは、ベラスケスの作品に影響を受けて『笛を吹く少年』を描いています。

エドゥアール・マネ 『笛を吹く少年』 / オルセー美術館
『オランピア』は近代絵画に繋がる重要な作品として、現代では高く評価されています。
写実主義とアカデミズム

王立絵画彫刻アカデミー / ルーヴル美術館
サロン(官展)は国家が主催する公式美術展覧会のことで、特にパリで行われるものは芸術界で最も権威のある場でした。
王立絵画彫刻アカデミーは、芸術を学問として専門的に教育する機関で、ルイ14世による国策の一貫として設立されました。
芸術家のエリート教育が行われ、解剖学、遠近法、美術史などのカリキュラムがありました。アカデミーの規範となったのは、新古典主義とロマン主義が統合された理想的な美です。

ウィリアム・アドルフ・ブグロー『ヴィーナスの誕生』 / オルセー美術館
彼らが重視したアカデミック美術とは、正確な線で描かれるデッサン、歴史や神話の画題など、正規教育と伝統を重んじる保守的なものでした。
それが王侯貴族やブルジョワ階級にとっての美の指標でもあり、画家として成功するためにはサロンでの評価が不可欠でした。
近代化・都市化が進むパリにおいて、労働者や貧困層など社会の現実を画題とした作品は受け入れられませんでした。
印象派との関係

エドゥアール・マネ 『カフェ・ゲルボワのデッサン』
多くの批判を浴びたマネですが、現代社会を描くスタイルが革新的だと支持する人々もいました。
若い画家や作家たちはマネを慕い、カフェで芸術談義を行うなど親交を深めます。
彼らは街の名前からバティニョール派と呼ばれ、後に「印象派」として確立していきます。
マネは「印象派の父」とされますが、自身も印象派の画家に学び、新しい手法を取り入れています。
ただし印象派展に絵を出品することはなく、一線を引いていました。

エドゥアール・マネ 『エミール・ゾラの肖像』 / オルセー美術館
マネはそんなゾラへの感謝を、肖像画として描いています。
背景に飾られているのは、自身の作品『オランピア』と、歌川国明の相撲絵です。
印象派に強い影響を与えた浮世絵を、西洋絵画に取り入れた先駆的存在がマネでした。

クロード・モネ 『草上の昼食』 / オルセー美術館
モネは『草上の昼食』をオマージュした作品を描いており、左側に座る男性はクールベがモデルになっています。
そしてミレーの描いた自然風景は、後の戸外制作や光の描写に大きな影響を与えています。
この作品からは、写実主義が印象派に繋いだ様々な要素を感じられると思います。

印象派とは?時代を築いた有名な画家の作品や歴史を徹底解説!
まとめ
現実社会を描くという写実派の強い意志は、また新たな芸術のかたちを作り出し、広がっていきました。
当時は対立構造となった新古典主義、ロマン主義、写実主義ですが、それぞれに美しさがあり、時代が進むにつれて評価も変動しています。
様々な作品に触れ、現代に生きる自分自身が何を感じるか、ぜひ確かめてみてください。
【おすすめ記事】
▶︎ 西洋美術史の流れを知る

西洋美術史とは?各時代の特徴や有名な作品をわかりやすく解説!

ロマン主義とは?その特徴や有名な絵画作品までわかりやすく解説

新古典主義とは?その特徴や有名な絵画作品までわかりやすく解説