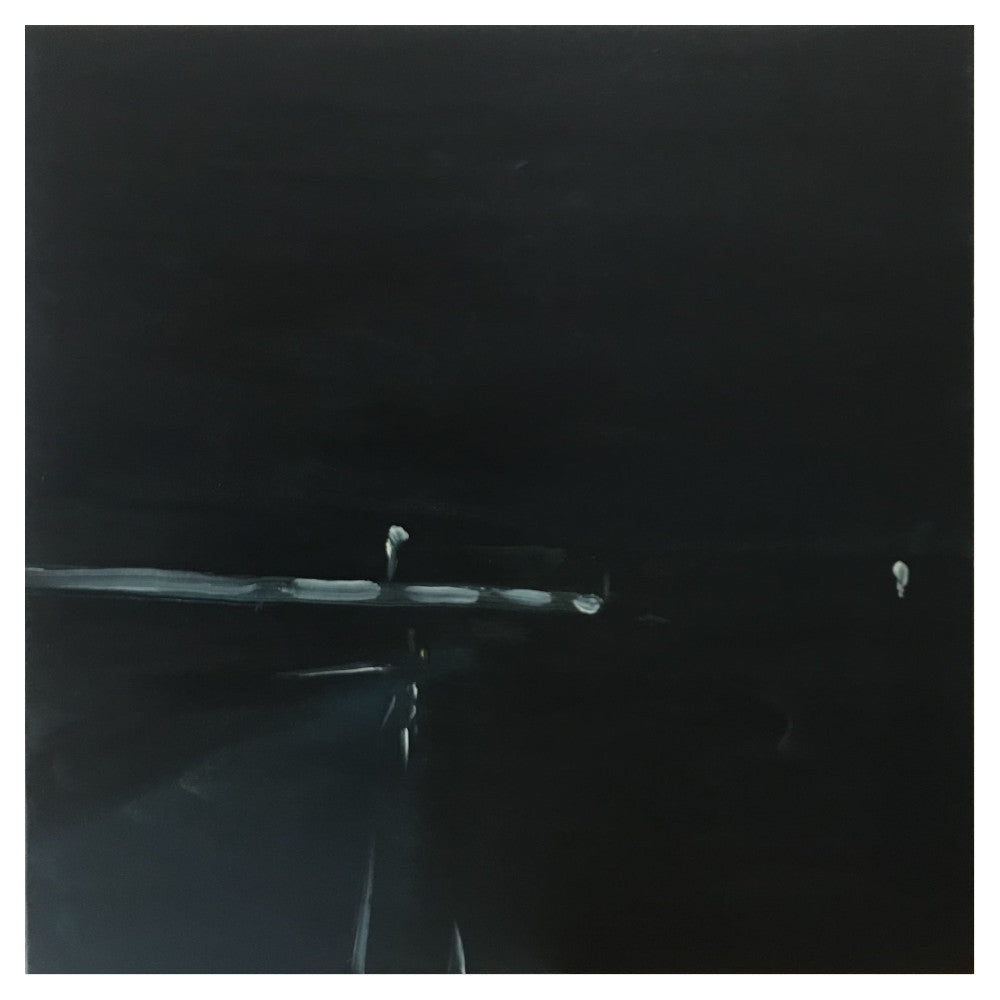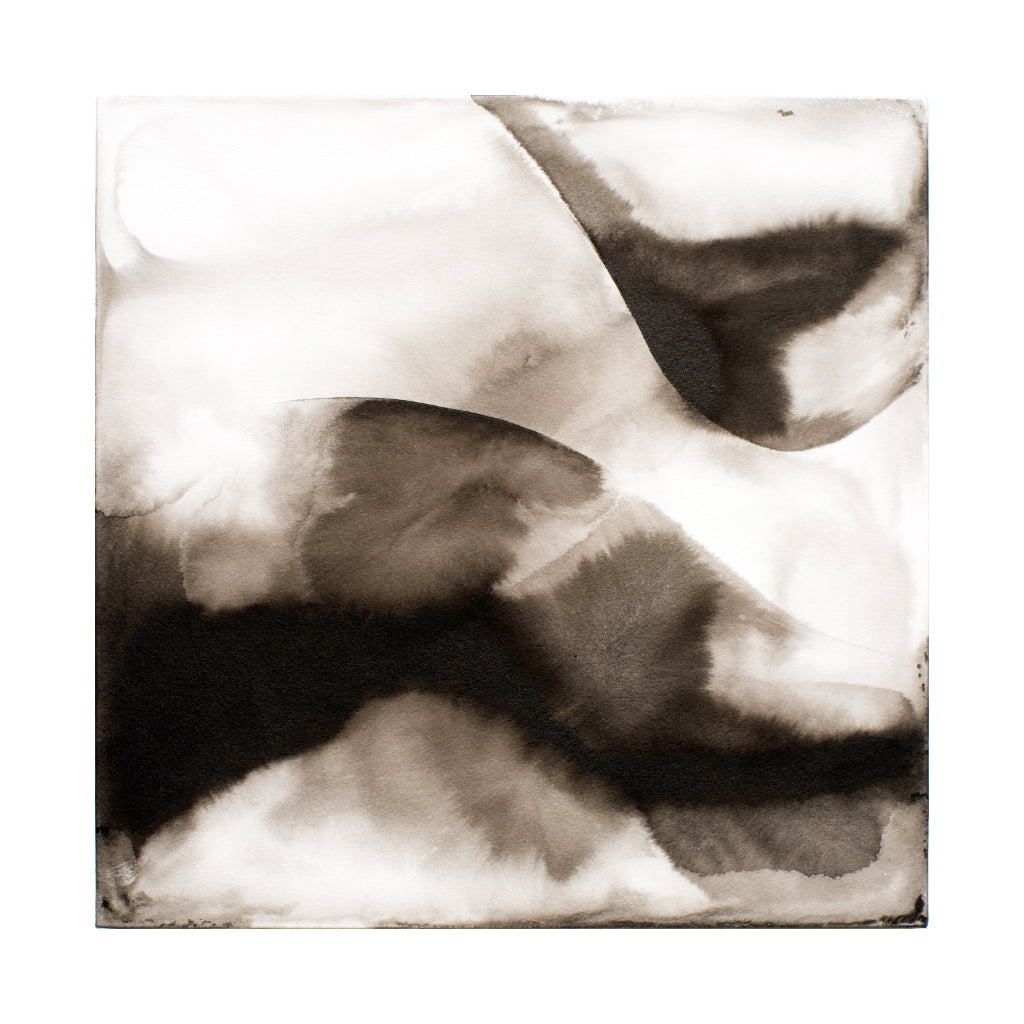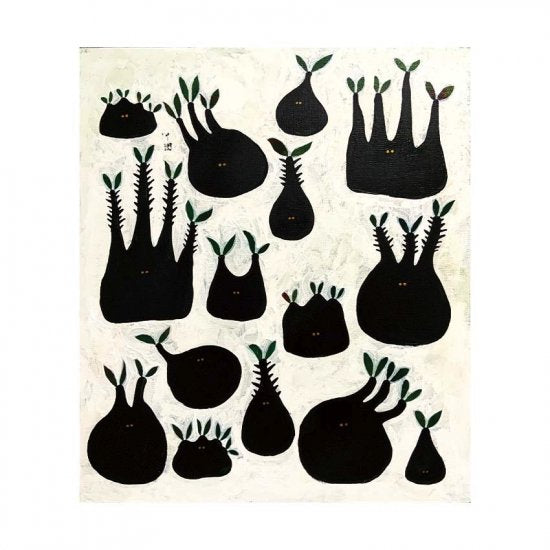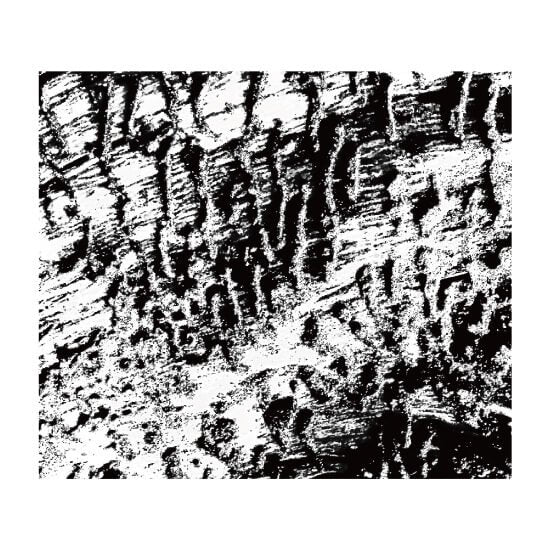ゴシックとは何か?建築様式と絵画を解説
投稿日:(月)

目次
こんにちは。WASABI運営事務局のシナモリです。
ゴシックという言葉は、何かしらで耳にしたことがあると思います。
例えばフォントのゴシック体や、ファッションのゴシック&ロリータ。
吸血鬼、フランケンシュタインなどの小説は、ゴシック文学と呼ばれます。
様々な解釈で表現されますが、美術史においては本来どのような意味を持つのでしょうか。
今回はその発祥や特徴について見ていきましょう。
概要:ゴシック様式とは?
ゴシックは、12世紀後半からフランスで発祥した芸術様式の総称です。
主に建築の特徴を表し、付随して絵画や彫刻に対しても用いられます。
代表的なゴシック建築には、フランス各地の『ノートルダム大聖堂』のほか、ドイツの『ケルン大聖堂』、イギリスの『ウェストミンスター寺院』、イタリアの『ミラノ大聖堂』など数々の世界遺産があります。

ノートルダム大聖堂 (パリ)

ケルン大聖堂 (ドイツ)

ミラノ大聖堂
ただし確立は建築よりも後であり、概ね美術史の後期ゴシック~初期ルネサンスに位置付けられます。

ジョット 『ユダの接吻』 / スクロヴェーニ礼拝堂

シモーネ・マルティーニ 『聖母子』 / メトロポリタン美術館
ゴシックは蔑称だった
ゴシック(Gothic)の語源は、3世紀頃ローマ帝国を脅かしたゴート族に由来します。
ゴート族はゲルマン民族の一派を指し、Goth-ic=ゴート的=野蛮なものという意味を込めた蔑称でした。
ゴシックはドイツ様式とも呼ばれ、ルネサンス時代、『芸術家列伝』で有名なジョルジョ・ヴァザーリらにより広まっていきました。

ジョルジョ・ヴァザーリ『自画像』 / ウフィッツィ美術館
実際、イタリアには『ミラノ大聖堂』以外にゴシック建築はあまりなく、元々のロマネスク様式に一部追加したり、独自の取り入れ方をしたものがほとんどです。
彼がここまで酷評したその特徴とは、どのようなものなのでしょうか。
ゴシック建築について
まず外観から主に挙げられる特徴として、高い天井・尖った形・装飾の多さ・ステンドグラスがあります。
① 高い天井

ノートルダム大聖堂 (アミアン)

ノートルダム大聖堂 (アミアン)
とにかく高く・大きく、それまでの建築と比べて破格のスケールで、訪れた人を圧倒します。
ゴシックの全盛期には、競い合うように大規模なものが建てられました。
アミアンのノートルダム大聖堂は高さ42.3m、全長145m、延床面積7700㎡にも及び、当時の市民1万人を収容できる程の広さです。
巨大な大聖堂は街のいたる所から見え、市民はもちろん、各地から訪れる信者たちにとっても目印となる存在でした。
リブ・ヴォールト

ケルン大聖堂
より高い建築を作れるようになった一因が、リブ・ヴォールトの採用です。
ヴォールトとはアーチ型の天井(穹窿)を指し、ロマネスク様式ではアーチ同士を垂直に組み合わせた交差ヴォールトが誕生します。

サント・フォア修道院
この交差ヴォールトに、リブ(肋骨)を付けて支えることで、荷重をさらに軽減することができました。
それによって壁も薄くなり、大きな窓で光を取り込めるようになります。

リブ・ヴォールトと交差ヴォールト

サント・シャペル (フランス)
リブの本数によって四分割、六分割になり、イギリスや18世紀後半以降では扇形ヴォールトなどに派生しています。

ピーターバラ大聖堂 (イギリス)
尖頭アーチ

ウジェーヌ・ヴィオレ=ル=デュックによる六分割リブ・ヴォールト
また、天井を支えるアーチは、先の尖った形になっています。
これは尖頭アーチと呼ばれ、建物の重さが本来横に向かう力を下方に伝える技術です。
従来の円形アーチと比較して、開口部を縦に広く取ることが出来るようになります。
この方法は、イスラムや中東の建築でも使われていました。

マスジェデ・ナスィーロル・モルク (イラン)
フライング・バットレス

フライング・バットレス(飛梁)
リブ・ヴォールトと併せて高さを叶えたのが、フライング・バットレスです。
天井や屋根を支えることで、建物の側壁には外向きに広がろうとする力がかかります。
そこで、もう一枚控え壁(バットレス)を置き、アーチをかけて荷重を流すことで構造全体の軽量化を実現しました。
これによって天井をより高く、大きな窓を増やすことが可能になりました。

ワシントン大聖堂 (アメリカ)
② 尖った形

シュテファン大聖堂 (オーストリア)
ピナクル
建物全体に尖った印象を与えているのが、控え壁の上に置かれるピナクル(小尖塔)です。
装飾として全体の高さや垂直性を演出するだけでなく、実益も兼ねています。
ピナクルによって、フライング・バットレスと控え壁の接合部分にかかる重量を相殺します。これにより力を下方向に流し、建物を安定させることができます。

イラスト出典 : Wikipedia
③ 装飾の多さ

ノートルダム大聖堂 (アミアン)
それまでの建築と比べて、外壁に作られた彫刻の数は圧倒的です。
主に聖書の物語を表現しており、キリストをはじめ聖人や天使など題材は豊富に存在します。
ヴァザーリの評した「無秩序」「混乱」は、装飾の多さを過剰と捉えたことが大きな理由だと思われます。

ノートルダム大聖堂 (パリ)

ミラノ大聖堂 (イタリア)
ピナクルや屋根は、クロケットと呼ばれる植物などを象った装飾が施され、外観の華やかさを一層演出しています。

クロケット
ガーゴイル

ノートルダム大聖堂 (パリ)
外壁によく見られるガーゴイルは、高い屋根から雨水を排出する役割があります。
雨樋の機能を持つ彫刻だけをガーゴイルといい、その他はキマイラやグロテスクと呼ばれます。
魔除けの装飾というだけでなく、雨粒を彫刻の先端で跳ね返すことで、壁に水滴が浸入するのを防ぎます。

口から雨水が流れる彫刻 (ガーゴイル)

ノートルダム大聖堂 (パリ)のキマイラ

出典:Disney Plus
また、19世紀に入ってから付け足されたグロテスクも多くあります。
現代ではゴシックに対して怪奇、ホラーといった要素が含まれやすく、このような怪物たちの姿は後世の文学などに影響を与えています。
④ ステンドグラス

ノートルダム大聖堂 (パリ)の薔薇窓
色ガラスを鉛でつなぎ合わせたステンドグラスは、ゴシック建築の大きな特徴です。
先述の方法で壁が薄くなったことにより、ステンドグラスも面積を広く出来るようになります。
当時のフランスでは、農業技術の発展によって仕事を失った人々が都市部に移住していました。
彼らは読み書きが出来ないため、聖書の内容を図像で表す必要がありました。
ステンドグラスや装飾など、大聖堂そのものが「石の聖書」と呼ばれる宗教美術の結集だったのです。

ノートルダム大聖堂 (パリ)

ブールジュ大聖堂 ステンドグラス
ステンドグラスは下→上、左→右へと物語が進んでいきます。
順を追って見ていくと、地上から天へと昇るような感覚になります。
このように技術や演出の進歩によって、それまでの建築様式が変化していきました。
ロマネスク様式との違い
ゴシック様式の特徴を挙げるにあたって、主に対比されるのがロマネスク様式です。
ロマネスクとは「ローマ風の」を意味し、10世紀末~12世紀頃ヨーロッパ各地で広まりました。
古代ローマ建築に回帰した様式で、修道院や大聖堂に多く見られます。
ピサの斜塔で有名なイタリアの『ピサ大聖堂』が代表的です。

ピサ大聖堂
ロマネスク建築の特徴は、石の重みを支えるための厚い壁や太い柱、半円形の天井にあります。窓を広く取ることが難しく内部は薄暗くなりますが、古代建築から受け継がれた重厚さが魅力です。

サント・マドレーヌ寺院 (フランス)
神の威厳を主に表現するロマネスクに対し、ゴシックはノートル・ダム(Notre-Dame)=我らが貴婦人、つまり聖母マリアに捧げる建築が多いのも特徴です。
ノートルダム大聖堂はパリだけではなく、世界各地に存在しています。
ロマネスクからゴシックへ

サン=ドニ大聖堂
最初期のゴシック建築といわれるのが、サン=ドニ大聖堂です。
初代司教・聖ドニを祀っており、フランス王家の墓所でもあります。

サン=ドニ大聖堂 王家の墓像
12世紀、修道院長シュジェールが建物の改築を指示します。
ファサード(建物正面)の薔薇窓や広い堂内、ステンドグラスの装飾など、彼の構想がゴシック様式の礎となったのです。
当時はまだ明確な力学論を確立しておらず、リブ・ヴォールトやフライング・バットレスなどの技術は、建築家たちの実験的な試みが奏功した部分があります。
その後も現在に至るまで、再建や補強工事、尖塔の修復が行われています。

シュジェール修道院長が描かれたステンドグラス
ロマネスク
・重厚で堂々とした雰囲気
・ビザンチン様式を発展させた壁画が多い
・建物それぞれに、個性やあたたかみが感じられる
ゴシック
・明るく壮麗な雰囲気
・ステンドグラスや立体的な装飾が多い
・規格で大量生産したパーツで、統一感が感じられる
大まかに特徴を見ていくと対照的に思えますが、様式が混在する建築も少なくありません。
フランスのシャルトル大聖堂は元々ロマネスク様式でしたが、1194年に火事で焼失した後、ゴシック様式で再建されました。

ノートルダム大聖堂 (シャルトル)
ロマネスク様式の良さを派生させた新しいスタイルであり、他の様式とも共存しているのがゴシック建築の面白さです。

モデナ大聖堂
中世における聖堂の役割
大聖堂は英語でカテドラルと言い、ラテン語で椅子を表すカテドラ(cathedra)に由来します。
椅子=権威の象徴、つまり司教の座がある場所という意味です。
聖堂建築の成り立ちは、キリスト教の布教に深く関わっています。

サンタ・チェチリア・イン・トラステヴェレ教会

洗礼者ヨハネの頸椎 / フィレンツェ大聖堂
元々は聖遺物(聖人の遺骸や、身に付けたもの)に最も価値がおかれ、それらを納める箱や建物は装飾要素でした。
聖遺物は本来礼拝者の目に触れなかったため、その価値や威光を示すために装飾、つまり建築が発展したのです。
大聖堂は信仰の対象であると同時に、人々が美術に触れるほとんど唯一の機会でした。

出典:NOTRE DAME TICKETS
聖堂建築には、主に3つの役割が挙げられます。
① 聖書の教えを説明すること
② 物語を視覚的に伝え、記憶に強く残すこと
③ 感情的に訴えかけて信仰心を深めること
そのために様々な装飾で聖書を図像化し、空間設計で演出効果を高めるねらいがありました。

ノートルダム大聖堂 (パリ)
ゴシック絵画について

ジョット・ディ・ボンドーネ
ゴシックの代表的な画家であるジョット・ディ・ボンドーネは、「西洋絵画の父」と呼ばれています。
ジョットの作品は革新的で、ビザンティンやロマネスクの平面的な絵画に写実性と立体感を取り入れました。
奥行きや感情表現の手法は、その後の西洋美術に大きな影響を与えました。

ジョット 『嘆き』 / スクロヴェーニ礼拝堂
描写の変化に大きく関わっているのが、サン・フランチェスコ大聖堂です。
ロマネスクとゴシックの建築様式が同在しており、ジョットやチマブーエ、マルティーニらによって壁画が描かれています。

サン・フランチェスコ大聖堂

サン・フランチェスコ大聖堂
聖フランチェスコの遺骨を収める建物ですが、彼の「キリストも同じ人間であり、肉体を持っていた」という教えが、絵画表現を大きく進歩させました。
前時代の壁画と比較すると、陰影がついてより人間らしくなり、未完成ながら奥行きを表現しているのがわかります。

コッポ・ディ・マルコヴァルド 天井画 / フィレンツェ洗礼堂

ジョット『荘厳の聖母』 / ウフィッツィ美術館
ロマネスク建築ではフレスコ壁画が中心に描かれましたが、ステンドグラスの導入で壁の面積は小さくなります。
そのため写本の装飾絵が発展したり、板絵(タブロー)の祭壇画が描かれるようになっていきました。

ランブール兄弟 『ベリー公のいとも豪華なる時祷書』より

ジェンティーレ・ダ・ファブリアーノ 『東方三博士の礼拝』 / ウフィッツィ美術館
ゴシックからルネサンスへ
12世紀後半頃、フランスでは国王フィリップ2世の権力が高まっていました。
首都パリの地位も向上し、知的活動の中心地となります。
経済的に豊かとなり、王侯貴族、聖職者、商人などの出資で多くの大聖堂が建てられました。
巡礼地として各地から人々が訪れて賑わうため、街の経済効果を狙った部分もあったようです。
しかし、13世紀後半にはその建設ラッシュも落ち着きを見せ始めます。
華やかなゴシックブームの裏には、重税に耐え切れなかった市民の暴動や、費用不足による建設の遅延など問題も発生していました。
この大聖堂建築による経済的衰退が、イタリアの発展に遅れをとった原因だとする説もあります。
ジョットの画風は国際ゴシックを経て広がっていき、後のルネサンスにつながる重要な起点となりました。

シモーネ・マルティーニ 『荘厳の聖母』 / プッブリコ宮殿
※国際ゴシック…14世紀後半以降、北方のゴシック様式とジョットの作風を融合した画家たちの総称。
マルティーニはアビニョン教皇庁で活躍し、ヨーロッパ全体にジョット風絵画を広めていった。
まとめ

出典:THE FASHION PARADOX
現代において「ゴシック系」といえば、黒を基調としたダークなイメージがあると思います。
これらは近代になって音楽や文学の影響を受け、発展していったものです。
ファッションにおけるゴシックは近現代の様々な要素が混ざっており、日本と海外でもニュアンスが異なります。
本来の意味にとどまらない、独自の表現スタイルになっています。
美術様式は古代への回帰と革新を繰り返しますが、各時代の特徴から人々が何を求め、何を光としていたのかが見えてきます。
何気なく使っていた言葉も、深く知ると思わぬルーツに辿り着き、現代とのつながりが面白く感じられるかもしれません。
【おすすめ記事】

世界の怖い絵20選|意味がわかると怖い絵から視覚的に怖い絵まで詳しく解説

孤高の天才、ミケランジェロの生涯
▶︎ 西洋美術史の流れを知る

西洋美術史とは?各時代の特徴や有名な作品をわかりやすく解説!