”学童用水彩絵具”との偶然の出会いが生んだ夢【アーティストの制作現場 Vol.05】
投稿日:(金)

目次
こんにちは! WASABI運営事務局のmeikoです。
【アーティストの制作現場シリーズ】も5回目に突入しました。
突然ですが皆さん、「学童用水彩絵具」をご存知ですか?
小学生なら誰もが使ったことのあるチューブ型のコレ。

亀井さんの私物です!
水の量次第で、透明感あふれる絵になったり、油絵のような重厚感も出せたりと、実はとっても優秀な絵具なんです。
そんな絵の具を使用する、学童用水彩絵具画家の亀井則道(カメイノリミチ)さんが今回の執筆者です。
『「絵は身近で、気軽に楽しめるもの」を広めていきたい。』という亀井さん。
地元の子どもたちを対象とした「アートにチャレンジ」という教室も開催しています。
学童用水彩絵具の伝道師とも言える亀井さんのコラムを、どうぞごゆっくりお楽しみください!
"学童用水彩絵具"との偶然の出会いが生んだ夢
はじめまして、学童用水彩絵具画家の亀井則道と申します。
今回は、私の活動をコラムで紹介する機会を頂き感謝しております。
人生初のコラムとなりますが、私が日々感じている学童用水彩絵具の魅力や、絵を楽しむ子どもたちへの想いを少しでも皆さんにお伝え出来たらと思い、慣れないWORDと向き合っております。
さて私は、上記のように『学童用水彩絵具』画家と名乗っております。
『学童用水彩絵具』、あまり聞きなれない言葉かもしれません。
しかし、誰しもが小学生時代に使ったことのある水彩絵具です。
「ぺんてる」「サクラクレパス」の商品を見たら、皆さんもピン!と来るかともしれません。

私の使用している絵具たち
誰もが使ったことがあるのに実はあまり知られていない…。
私は風景画を通してその魅力を伝える活動をしています。
水彩画を描き始めたきっかけ
そのきっかけは、ある日の思いつきからでした。
2017年1月、人生で初めてインフルエンザにかかりました。
これはしばらく暇になるなぁと、病院の帰り道にふと購入したのが学童用水彩絵具だったのです。
絵筆を手にしたのは、おそらく学生時代の図工や美術の授業以来。
当時アパレル系の商社で働いていた私ですが、帰宅後にはもちろん、出勤前の5分でも絵筆を取り、週末になれば何かから解放されたかのように「絵が描ける!」という喜びにあふれる日々が始まりました。
アパレル当時の知識から、色相環と明度・彩度、染料の三原色など色彩知識の下地はありましたが、水彩画については全て独学。ましてやここまで描き続けるとは、当時は想像もしていませんでした。
私が『学童用水彩絵具画家』を名乗る理由
学童用水彩絵具は、1950年に総合文具メーカーのサクラクレパスが「子どもたちでも扱いやすく、思い通りに描ける絵具を」との想いから開発された、日本特有の絵具です。
 株式会社サクラクレパス『サクラ マット水彩12色』
株式会社サクラクレパス『サクラ マット水彩12色』
ちなみにその絵具に合わせるように1958年開発されたのが、誰もが目にしたことのあるマルマンの『図案スケッチブック』です。私の絵はすべて、マルマンの図案スケッチブックに描いています。

マルマン株式会社『図案スケッチブック』
そして1960年頃、学童用水彩絵具の最大手のぺんてるが『エフ水彩』を開発しました。
 ぺんてる株式会社『エフ水彩』
ぺんてる株式会社『エフ水彩』
これらは「学童用」との名称から子ども向けの絵具と認知されています。しかし、
・水を多めにすれば、透明水彩のような表現に
・水を少なめにすれば、重ね塗りもでき、油絵感覚な仕上がりに
なるのです。それは「半透明水彩絵具」とも呼ばれ、良い意味で「どっちつかず」の成分比率が成せる技だと言えます。

加えて、こんな魅力もあります。
・水で洗えて、ニオイも少ない
・町の文房具店でも買える手軽さ・気軽さ
・安全安心の品質!※
(ウラ話)
地元の立ち飲み屋で隣り合った方が、偶然にもぺんてるの『エフ水彩』製造担当者で…
そのご縁で、ぺんてる茨城工場様に訪問機会をいただき、学童用水彩絵具への知識も深めました。
それぞれの絵具に、それぞれの特性と優位性がありますが、私にとっては、学童用水彩絵具がとても使い心地の良い絵具なのです。
「学童用」という性格上、絵具そのものに選ばれている色は、画家が使用する絵具よりも「子どもっぽい色」になっています。
それは、子どもたちに色名を覚えてもらう教材として、各社がJIS規格に準じた色と色名に合わせた色を絵具に採用しているためです。
ですが、そんな絵具も、混ぜればいいのです!
それこそが、絵具の楽しさであり、魅力です!

学童用水彩絵具を使った500色の混色表
しかし現実は、小学校卒業と共に、使われる機会を失う学童用水彩絵具。
日本が開発したこの絵具のすばらしさを、もっと多くの子どもたちや、海外の方にも触れてもらいたい。
実際に、Instagramの海外のフォロワー様より、「君の使ってる絵具の種類は何なんだい?」と興味深げな問い合わせを、定期的に頂いています。


KESHIKI on the tableシリーズ「小川」より
海外の方からみても、そう感じていただける絵具なんだ!
そんな想いから、『学童用水彩絵具画家』を名乗るようになりました。
「アートにチャレンジ」学童用水彩絵具を広めるための取り組み
現在、私の地元の水戸市内の学童さん・放課後こども教室や、近所のお子様へ向けて「アートにチャレンジ」という会を定期的に開催しています。

放課後こども教室での風景(水戸こどもの劇場にて)
一般的に、小学校の写生大会では八つ切り画用紙が1枚配布されますが、私の「アートにチャレンジ」の際は、A4サイズの用紙を何枚でも交換OKにしています。
少し小さい画用紙にすることで、作品完成までの時間を短くし、失敗を恐れずに何枚でもチャレンジできますし、1日に2枚、3枚と描き上げる生徒さんもいます。

放課後こども教室での風景(水戸こどもの劇場にて)
そのようにして、描くことの経験値や成功体験をどんどんと増やしてほしいと思っています。
ただ小学校低学年だと、お箸よりも長い筆も使いこなすのが難しいときもあります。
そんなときは100均一ショップで購入できる、パフやブラシ、歯ブラシ、綿棒などで、楽しくアートに触れられるように心がけています。


100均一で購入したアイテム
それでも、小さい生徒さんの中には「私、、、絵が下手だから。。。」とつぶやく子がいます。
まだ、7、8歳のお子様が…。
それは、本当にその子が自発的に感じたことなのか?
もしかしたら、周りの大人の反応や言葉で、自分は絵が下手と思い込んでしまったのではないか?
絵画には、正解もないですし、ましてや子どもたちには、自由な発想で、創作して欲しい。
その想いから、"指導"でも、教室のように堅苦しく教えるでもなく、
クイズ形式の色混ぜゲームや実験を通し、絵具の三原色や、くろ絵具を使うコツなどを楽しく伝えています。
そして、「これは○○を描いているのかな?」のような答えを決めつけた声掛けはしないように心がけています。
(画家としての肩書きはもちろんですが、何よりも水彩絵具に触れる機会の多い子どもたちが絵を楽しんでくれること、それを一番大切にしています。)

100均アイテムを使った子ども向け参考画
KESHIKI on the table への想い
「絵を飾りたい」
そんな思いが頭によぎったとき、その経験の少ないない方は、
「うちに飾る場所がある?ない?どこがいい?」
「飾り方って難しいの?めんどくさいのかも…」
「額は自分で買うの?どこで買うの?サイズは?そもそも額に入れなくてはいけないの?」
なんて疑問が浮かぶかもしれません。
写真やお花は気軽に飾れるのに、「絵画」となるとどうしても難しく感じてしまいます。
または「大切に保管しましょう」と、飾られることなく暗室で過ごすこととなる「絵画」もあります。
そんな方へ向けて私は、KESHIKI on the tableシリーズを制作しています。
PCデスクの上や、カウンターキッチンの調味料の隣、お手洗い場などのインテリアとして、さまざまな日常の中に溶け込む作品シリーズです。
届いた瞬間すぐに飾れるように、小さな台付きのフォトフレームに入れています。

私の水彩画は、強いメッセージや独創性があるものではありません。
どこかで出会えそうな『KESHIKI=景色』ばかりです。
一つだけこだわりをお伝えするならば、私は風景画の中には、人物も、サインも入れないという点でしょうか。
『KESHIKI』の中に入り込んで、風や、日差しや、草むらの踏み心地を感じたり、「こんなところで、深呼吸したい。昼寝してみたい!」と観て頂く方に思っていただけたら、それほど嬉しいことはありません。
季節や気分にあわせて、小さな『KESHIKI』を楽しめる。そんなシリーズとなっています。
(KESHIKI on the tableシリーズはこちらから)
最後に
絵を描くことって難しい…特別なこと…
そう感じる方も多いのかもしれません。
絵を描くことが、歌を唄うことと同じように、もっと身近な存在になって欲しい。
その初めの一歩のお手伝いができればと、想いながら、
自らも絵筆を手にしています。
お読みいただきありがとうございました。

私の使う絵具
ARTIST DATA

亀井則道
2017年1月に人生で初めてのインフルエンザにかかり、その自宅待機期間に独学で水彩画作成を開始。画材は、日本小学生なら誰でも一度は使った経験のある「学童用水彩絵具」を使用。
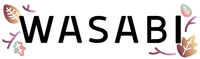
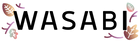





















※実例 ぺんてる茨城工場様
【健康面】
・国際標準化機構(ISO)のsafty of toysの基準以上に厳しい自社基準での原料手配
→絵具の主原料でもある顔料の重金属含有量を最小限に抑える努力
【環境面】
・地域的にも茨城県霞ケ浦水質保全条例もあるが、主的に工場排水の「環境への配慮」した生産体制
→ぺんてる社の学童用水彩絵具のすべてが、霞ヶ浦に隣接した茨城工場でのみ生産